
小さな子どもは、本当に面白いことをたくさんやります。しかし、それを面白いと思えるかどうか、それが良いと思えるかという大人側の問題があります。
ティッシュをまき散らす理論

上の娘がまだ1才~2才の頃だったと思います。
目を離した隙に、ティッシュボックスからティッシュを取り出し、ポイと投げるという動作を繰り返していました。居間はティッシュだらけです。
私はそれを「楽しそうだからいいね!」と見ていたのですが、ティッシュはまき散らされるし、そのティッシュは別に使われるわけでもないし、ただの遊び道具として存在していたため、普通は「そんなことしちゃダメ!」となるわけですが、私は「いいね!」と思ってやらせていました。
その当時の私なりの考えは、次のようなものでした。
①ティッシュを出しての遊びは安全である。
②ティッシュを出している娘の姿は楽しそうである。
③ティッシュは遊び道具として完璧にその役割を果たしている。
④ティッシュは遊び道具としては安価である。
⑤以上の理由から、邪魔をしてはいけない。
本をまき散らす理論

上の娘が同じ頃、私の部屋の本をまき散らして遊んでいました。
キレイに並べてあった本を次から次へと取り出し、カバーを外してはポイと捨てるのです。おかげさまで、私の部屋は本が床にまき散らされ、全てのカバーが外されていました。
私はそれを「楽しそうだから、ま、いっか。」と見ていました。後で私が片づければいいだけです。それで、めんどくさかったのですが、きちんと片づけたのです。すると、数日後、またやってきて本をまき散らします。こんなことを3回ほど繰り返しました。
その当時の私なりの考えは、次のようなものでした。
①本をまき散らす遊びは安全である。
②部屋は散らかるが、それは私の部屋なので誰の迷惑にもならない。
③本は少し傷みますが、道具は全て使えば傷みます。
④所詮は本です。本の立場に立てば、読まれる以外にも玩具になるという2つの役割を果たしたことになる。
⑤以上の理由から、邪魔をしてはいけない。
シールを無駄遣い理論

上の娘がもう少し大きくなった頃、シールが好きでした。しかし、シールを集めるのではなく、自分のシールをすぐに貼るのです。使っちゃうということは、なくなっちゃうということで、少しもったいないような気もします。
その当時の私なりの考えは、次のようなものでした。
①シールは、そもそも貼るために存在している。
②シールを貼るのは面白いようである。
③シールの貼り方は汚らしいが、どうやら娘なりのこだわりがあるようだ。
④やらせてみて分かったのは、だんだん貼るのが上手になっている。
⑤続けてみて分かったのは、娘なりに貼るシールを選んでいるようだ。
⑥以上の理由から、邪魔をしてはいけない。
やりたいようにやらせる方針
以上のように、私は娘がやりたいことをやらせるという方針でした。私は邪魔をしない。私は見守る。私は安全面だけは配慮する。
遊びの中にたくさんの発見があり、集中して夢中になってやっている姿がかわいらしくて、子どもらしくて、目を輝かせているからです。
ところが、この方針は少々難しさも伴います。子どものペースということは、大人のペースではありませんし、散らかした物を片づける必要もあります。見守るというのは、見ていなければいけませんし、だいたい小さな子どもがやることなど、意味不明です。
しかし、意味不明なのは大人側から見たらそうなるというだけで、子どもにとっては意味があるのだろうなと思っていました。
これが今から10年も前の話です。
先日、モンテッソーリの教育という本を読んでいましたら、これらの実践を裏付ける記載があったので、私は「やっぱりそうでしょ!」と嬉しくなりました。なぜなら、当時の私のこの理論は、あまり評判が良くなかったからです。
ちなみに、他にもたくさんの事をやっていました。
「お風呂で遊ぶ」「水で遊ぶ」「何でも拾っちゃう」「なんでも散らかす」「DVDをケースから取り出して投げる」「階段を上りたがる」などなど。
安全面だけ気をつけて、とりあえずやらせてました。
モンテッソーリの教育
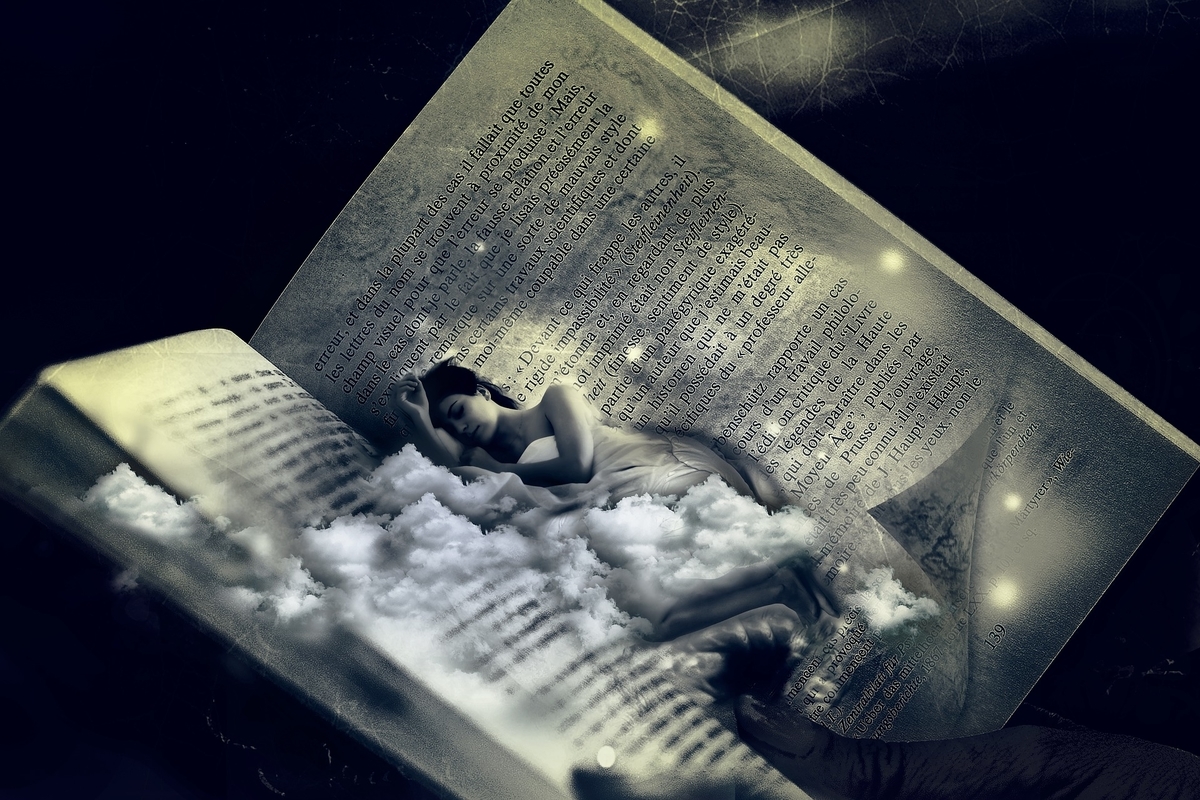
今からおよそ100年前に提唱されたモンテッソーリの幼児教育理論は、残念ながら日本では普及していませんが、一部で実践されているようです。それによれば、モンテッソーリ幼児教育理論を実践すれば、集中力と知的好奇心が旺盛な子に育つことが認められています。聞いた話では、将棋の藤井颯汰さんもモンテッソーリ理論の保育園出身だそうです。
では、モンテッソーリの幼児教育理論とは何かということを簡単に説明します。
モンテッソーリは0才から3才までの幼児の学習獲得期を敏感期として発見します。その敏感期においては、大人では不可能な速度で感覚的に霊感的に物事を吸収、理解していくというのです。それは教えられるものではなく、子ども自身が自分で発見する過程であるから、環境を整えて邪魔をしなければ、子どもは自然の衝動をもとに、そして発達の法則、自然の法則にしたがって成長するというわけです。
『モンテッソーリの教育』という本から一部を抜粋します。
モンテッソーリ:著 林信二郎・石井仁:訳 あるなろ書房 より
「子どもは心身の活動に対する本質的な熱望が妨害されており、いつも抑圧されているという苦悩を経験しているのです。」 p.24
「重要な問題は、子どもに援助が与えられ過ぎていることです。そのような援助は、事実上の妨害になります。(中略)私たちは、ある範囲を超えて子どもに与えられる援助は、子どもの発達の障害になるということを指摘したいと思っています。」 p.24
「植物も、動物や子どもがそうするのと同じように、その独自の発達の法則に従います。」 p.34
「それぞれの生命は1つの統一体であり、それに続くそれぞれの時期は、前の時期に確立されたもののさらなる発展に過ぎないものです。(中略)生まれたあとの最初の3年間の子どもの発達は、子どもの生命の中で、それ以前やそれ以後のどの時期に比べても、激しさや重要さの点で比べものにならないものがあります。」 p.45
「0歳から3歳までの生命の最初の時期の環境の変化、適応、成就、そして征服ということについて考えてみると、それは実質的には、3歳から死ぬまでを合わせたそれに続く全期間よりも長い期間だということになります。この理由によって、これら3年間は全生涯と同じくらい長いと見なすことができます。」 p.46
まだまだご紹介したい内容があるのですが、長くなってしまうので、ごくごく簡単に3つに絞って説明します。
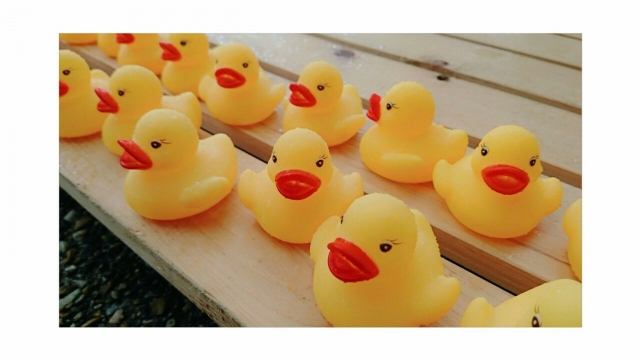
1 0歳~3歳が超重要であるということ。だから幼児教育。
2 子どもの発達は自然の法則に従って自然に起こる。
3 だから、なるべく邪魔をしないこと。
以上の3つが骨子となります。3歳以降も成長は続きますが、それらの成長は、前の時期を土台として起こるものに過ぎないので、0歳~3歳までに自然の法則に従って見守ることができれば、それ以後は集中力と知的好奇心をもって取り組める子になるというわけです。
最初に述べた「ティッシュまき散らす理論」「本まき散らす理論」「シール無駄遣い理論」は、結局のところ、私は邪魔をしていなかったのです。
その当時は、そこまで深い理論に裏付けされたものではありませんでしたが、結果としてそうだったのだなと、嬉しくなりました。
モンテッソーリ教育からは、他にもたくさんの現象を説明することができますが、それらはまたの機会にします。
今回は、邪魔をしないということが、とても大切だという記事でした。